アポスティーユとは?【図解】必要な場面と申請手続きの全手順を解説!

海外留学や就職、国際結婚の手続きで「アポスティーユ」という言葉を目にし、戸惑っていませんか?「公印確認との違いは?」「自分で申請できる?」といった疑問や不安を抱えている方も多いでしょう。
この記事では、アポスティーユに関するあらゆる疑問にお答えします。ビザ申請の専門家である行政書士が、外務省の公式情報に基づき、制度の概要から必要となる場面、具体的な申請手順まで、図解を交えて丁寧に解説します。
プロの視点から、失敗しないための注意点やケーススタディも紹介。最後まで読めば、ご自身の状況で何をすべきかが明確になり、自信を持って手続きを進められるようになります。
アポスティーユ・公印確認・領事認証の違いが一目でわかる比較表

日本の公文書を海外へ提出する際には、「アポスティーユ」「公印確認」「領事認証」の3つの証明手続きが存在します。いずれも日本の公文書が正規のものであることを証明する手続きですが、提出先の国に応じて手続きが異なります。
まずは、それぞれの違いを比較表で確認しましょう。
| アポスティーユ | 公印確認+領事認証 | |
|---|---|---|
| 対象国 | ハーグ条約加盟国 | ハーグ条約非加盟国 |
| 手続き | 日本の外務省だけで完結 | 外務省の「公印確認」後、駐日外国領事館の「領事認証」が必要 |
| 特徴 | 手続きがシンプルで早い | 手続きが2段階で複雑 |
アポスティーユとは?【かんたん解説】
アポスティーユとは、日本の公文書を海外で有効なものとするための「外務省による付箋(ふせん)状の証明書」です。正式名称は「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」に基づく証明を指します。
通常、市役所が発行した戸籍謄本をそのまま海外の機関に提出しても、それが正規の書類か判断できないため受理されません。そこで、外務省が「この公文書は日本の正規の機関が発行したものです」というお墨付きを与えるのがアポスティーユの役割です。
手続きが簡略化されるハーグ条約の仕組み
アポスティーユを理解する鍵が「ハーグ条約」です。この条約は、加盟国間における公文書のやり取りを簡素化するための国際的な取り決めです。
ハーグ条約に加盟している国へ書類を提出する場合、日本の外務省でアポスティーユを取得すれば、提出先国の駐日大使館(領事館)による認証が不要になります。これにより、認証にかかる時間と手間を大幅に削減できます。アメリカ、イギリス、韓国、ドイツ、フランスなどが主な加盟国です。
【フローチャート付】アポスティーユか公印確認か、どちらが必要?
ご自身のケースでどちらの手続きが必要か、以下のフローチャートで簡単に判断できます。
【Step 1】 書類の提出先は「ハーグ条約加盟国」ですか?
→ YES の場合:「アポスティーユ」を取得します。手続きは日本の外務省のみで完了です。
→ NO の場合:次のStep 2に進みます。(例:中国、ベトナム、インドネシアなど)
【Step 2】 「公印確認」と「領事認証」の2段階の手続きが必要です。
まず日本の外務省で「公印確認」を受け、その後、日本にある提出先国の大使館・領事館で「領事認証」を受けます。
アポスティーユが必要になる7つの具体例
アポスティーユは、国際的な活動の様々な場面で必要とされます。ここでは個人と法人に分け、代表的な7つのケースを紹介します。ご自身の状況と照らし合わせ、どのような場合に手続きが必要となるか確認してみましょう。
1.【個人】海外の大学へ留学するとき(卒業証明書・成績証明書など)
海外の大学や大学院へ出願する際、日本の大学の卒業証明書や成績証明書の提出を求められることがあります。これらの書類が正規のものであることを証明するため、提出先の教育機関からアポスティーユを要求されるケースが非常に多いです。
特に、私立大学の証明書は「私文書」扱いのため、一度公証役場で認証を受けてから外務省へ申請する必要があります。
2.【個人】海外で就職・転職するとき(卒業証明書・各種免許状など)
海外企業へ就職する際も、最終学歴を証明する卒業証明書や、医師・看護師といった国家資格の免許状にアポスティーユを求められることがあります。これは採用企業が応募者の経歴・資格の真偽を確認するために必要となります。就労ビザの申請要件として、アポスティーユ付きの書類を求める国もあります。
3.【個人】国際結婚をするとき(戸籍謄本・婚姻要件具備証明書など)
外国籍の方と海外の方式で結婚する際には、独身であることや日本の法律上の婚姻可能年齢に達していることを証明するため、「戸籍謄本」や「婚姻要件具備証明書」を提出します。これらの公文書について、提出先国の機関が有効性を認めるためにアпоスティーユを要求します。
4.【個人】海外の永住権を申請するとき
海外へ移住し、その国の永住権を申請する際には、身元を証明する多くの公文書が必要となります。例えば、出生を証明する「戸籍謄本」や、犯罪歴がないことを示す「警察証明書(犯罪経歴証明書)」などです。これらの公文書は、申請先の国の移民局などからアポスティーユ付きでの提出を求められるのが一般的です。
5.【法人】海外に支店や子会社を設立するとき(登記簿謄本・定款など)
日本の法人が海外に拠点を設ける際には、その会社が日本で法的に存在することを証明する必要があります。そのために、法務局が発行する「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」や、会社の根本規則である「定款」にアポスティーユの取得が求められます。これらの書類は、現地の法人登記や銀行口座開設に不可欠です。
6.【法人】海外企業と契約を結ぶとき
国際取引、特に政府機関などが関わる大規模な契約では、契約締結者の代表権を証明する書類を求められることがあります。この場合、「代表者事項証明書」や「印鑑証明書」に、公証人の認証とアポスティーユを付して提出する必要があります。これにより、契約の正当性と信頼性を担保します。
7.【法人】国際的な裁判で証拠を提出するとき
万が一、海外企業と法的な紛争が生じ、国際裁判で日本の公文書や私文書を証拠として提出する際にはアポスティーユが必要です。契約書や議事録、会計書類などがこれにあたります。裁判所がその文書を正式な証拠として受理するために、アポスティーユによる証明が不可欠となります。
【5ステップで完了】アポスティーユ取得の具体的な申請方法
アポスティーユの申請は、正しい手順を踏めばご自身でも可能です。ここでは、誰でも手続きを進められるよう、5つのステップに分けて具体的に解説します。
STEP1:提出先の国がハーグ条約加盟国か確認する
最初に、書類を提出する国がハーグ条約の加盟国かを確認します。この確認が手続きの出発点です。加盟国であればアポスティーユ、非加盟国であれば公印確認+領事認証と、必要な手続きが決まります。
加盟国の一覧は、外務省のウェブサイトで最新情報をご確認ください。中国やベトナム、UAEなどは非加盟国です(2025年時点)。
STEP2:アポスティーユの対象書類か確認する(公文書と私文書)
次に、認証を受けたい書類が「公文書」か「私文書」かを確認します。外務省で直接アポスティーユを取得できるのは、原則として発行から3ヶ月以内の「公文書」のみです。
私文書の場合、まず公証役場で「認証」を受けた後、法務局で「公証人押印証明」を取得することで公文書として扱われ、外務省での手続きに進むことができます。(この公証役場と法務局での手続きをまとめて行える「ワンストップサービス」もあります)
公文書の例(戸籍謄本、登記簿謄本など)
- 国または地方公共団体の機関が発行する書類(例:戸籍謄本、住民票、納税証明書)
- 法務局が発行する書類(例:履歴事項全部証明書)
- 国公立学校の卒業証明書、成績証明書
私文書の例(公証役場での認証が必要)
- 私立大学の卒業証明書、成績証明書
- 企業が作成した契約書、定款
- 翻訳会社の翻訳証明書
これらの私文書は、お近くの公証役場で認証を受ける必要があります。
STEP3:申請に必要な書類を準備する(申請書・本人確認書類など)
申請に必要な書類を漏れなく揃えましょう。不備があると手続きが遅れる原因になります。基本的に必要な書類は以下の通りです。
- 証明が必要な公文書(発行から3ヶ月以内):原本
- 申請書:外務省のウェブサイトからダウンロード
- 本人確認書類:運転免許証やマイナンバーカードなど
- 返信用封筒(郵送の場合):切手を貼り、宛名を記入したもの
STEP4:外務省の窓口へ申請する(東京・大阪)
書類が揃ったら、外務省の窓口に直接持参するか、郵送で申請します。急ぐ場合は窓口申請がおすすめです。
窓口は東京(本省)と大阪(分室)の2ヶ所です。郵送の場合は、東京の外務省国内申請室宛に送付します。どちらの方法でも手数料は無料です。
申請窓口の場所と受付時間
- 外務省本省(東京):東京都千代田区霞が関2-2-1
- 外務省大阪分室:大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
- 受付時間:いずれも平日午前9時15分~12時15分、午後1時15分~4時00分
郵送での申請方法と注意点
郵送の場合は、必要書類一式を封筒に入れ、外務省の指定する宛先へ郵送します。追跡可能な簡易書留などで送ると安心です。
STEP5:アポスティーユが付与された書類を受領する
申請後、不備がなければアポスティーユが付与された書類が返却されます。窓口申請の場合、通常は翌開庁日に交付されます。
郵送申請の場合は、外務省に書類が到着してから返送されるまで10日~2週間程度を見込んでおきましょう。時間に余裕を持った申請が重要です。
【プロが教える】アポスティーユ申請の注意点とケーススタディ
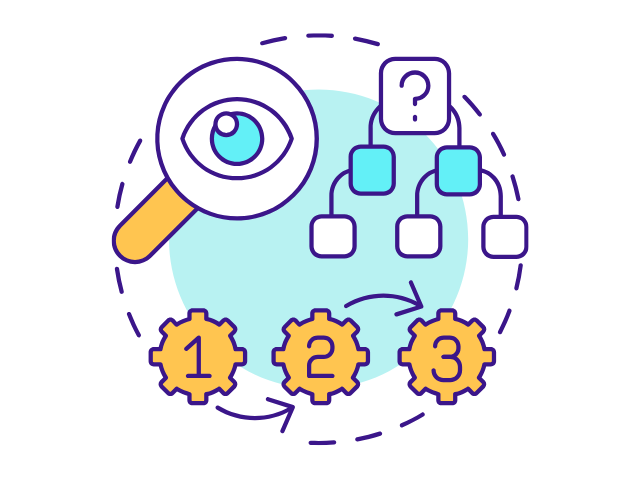
ここまではアポスティーユの基本情報を解説しました。しかし、実際の申請では個別の状況に応じた判断が求められます。この章では、専門家の視点から、陥りがちな失敗例や具体的なケーススタディを交えて、申請時の注意点を解説します。
【ケーススタディ1】IT企業が米国法人設立のため登記簿謄本を取得する場合
IT企業がアメリカに現地法人を設立するケースで見ていきましょう。まず、法務局で会社の「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」を取得します。これは公文書なので、公証役場を経由する必要はありません。次に、外務省のウェブサイトから申請書をダウンロードして記入し、登記簿謄本と一緒に外務省の窓口または郵送で申請します。アメリカはハーグ条約加盟国のため、このアポスティーユ付き登記簿謄本を提出すれば、正式な書類として現地で受理されます。
【よくある失敗例①】私文書を直接、外務省に申請してしまう
よくある失敗が、私立大学の卒業証明書などを、公証役場での認証を経ずに外務省へ直接申請してしまうケースです。これらは私文書のため、外務省は直接証明を発行できません。必ず事前に公証役場で認証を受け、法務局の公証人押印証明を取得するステップを忘れないようにしましょう。
【よくある失敗例②】有効期限切れの公文書で申請してしまう
外務省がアポスティーユの対象とするのは、原則「発行後3ヶ月以内」の公文書です。事前に取得していた戸籍謄本などの発行日をよく確認しましょう。また、提出先機関が「発行後1ヶ月以内」など、より厳しい期限を設けている場合もあるため、そちらの規定も併せて確認が必要です。
【よくある失敗例③】翻訳文への認証プロセスを間違える
書類に翻訳文を添付する場合、その認証プロセスで混乱する方が少なくありません。翻訳文自体は私文書のため、翻訳者が「私が翻訳しました」と記した宣言書に公証人の認証を受け、アポスティーユを取得するのが一般的です。この時、認証の対象はあくまで「翻訳者の署名」であり、翻訳内容の正確性を保証するものではない点を理解しておくことが重要です。
アポスティーユ取得にかかる費用と期間の目安
アポスティーユを取得するにあたり、どれくらいの費用と時間が必要か気になるところです。ここでは、自分で申請する場合と専門家に依頼する場合、それぞれの目安を解説します。
1.【費用】自分で申請する場合(手数料は無料)
外務省に支払うアポスティーユの発行手数料は無料です。費用がかかるのは、主に手続きに必要な以下の実費部分です。
- 公文書の取得費用:戸籍謄本(450円)、登記簿謄本(600円)など
- 郵送費:往復のレターパック代(約1,040円)など
- 交通費:窓口に直接行く場合の電車代など
- 公証人手数料(私文書の場合):1通あたり11,500円程度
2.【費用】行政書士に依頼する場合の料金
行政書士などの専門家に依頼する場合、代行報酬が発生します。報酬額は事務所により様々ですが、一般的に1通あたり15,000円から30,000円程度が相場です。複数の書類を依頼する場合や、翻訳、公証役場での手続きを含む場合は料金が変動するため、事前に見積もりを確認することが大切です。
3.【期間】申請から受領までにかかる日数(窓口と郵送の違い)
申請から書類を受け取るまでの期間は、申請方法によって大きく異なります。
- 窓口申請の場合:原則、申請した翌開庁日に交付されます。最もスピーディーな方法です。
- 郵送申請の場合:外務省に書類が到着してから発送されるまで、おおむね10日~2週間程度かかります。往復の郵送日数も考慮すると、さらに時間が必要です。
提出期限が迫っている場合は、窓口申請か、スピード対応が可能な専門家への依頼を検討しましょう。
アポスティーユに関するよくある質問(Q&A)

最後に、お客様から特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。疑問の解消にお役立てください。
- Q1. 自分で申請するのは難しいですか?
- A. 手続き自体は可能ですが、時間と手間がかかります。特に、私文書の認証が必要な場合や、複数の書類を扱う場合はプロセスが複雑になります。重要な書類で失敗が許されない場合は、初めから専門家に依頼する方が確実です。
- Q2. アポスティーユに有効期限はありますか?
- A. アポスティーユ自体に有効期限はありません。しかし、証明の対象である公文書(戸籍謄本など)には、提出先機関から「発行後3ヶ月以内」といった期限を定められていることがほとんどです。申請前に、必ず提出先に有効期限を確認してください。
- Q3. 提出先がハーグ条約に加盟していない場合はどうすればいいですか?
- A. 「公印確認」と「領事認証」の2段階の手続きが必要です。まず日本の外務省で「公印確認」を受け、その後、日本にある提出先国の大使館または領事館で「領事認証」を取得します。アポスティーユより手続きが複雑で時間もかかるため、注意が必要です。
- Q4. どの書類にアポスティーユが必要か分かりません。
- A. 最も確実な方法は、書類の提出先機関に直接確認することです。必要な書類や認証の種類は、国や提出先の機関(学校、企業、政府機関など)によって異なります。「アポスティーユ付きの戸籍謄本を1通」といったように、具体的に確認することが手戻りを防ぐ一番の近道です。
まとめ:アポスティーユ手続きは複雑!お困りの際は専門家への相談が確実です
この記事の重要なポイント
本記事では、アポスティーユの基本から申請方法、注意点までを解説しました。重要なポイントは以下の通りです。
- アポスティーユはハーグ条約加盟国向けの手続き
- 非加盟国へは「公印確認+領事認証」が必要
- 私文書は、先に公証役場での認証が必要
- ご自身での申請は費用を抑えられるが、時間と手間がかかる
専門家への依頼が確実な理由
専門家へ依頼する最大のメリットは、時間と手間を省き、手続きの失敗リスクをなくせる点にあります。慣れない手続きでは書類の不備やプロセスの誤りが起こりがちで、想定外の時間を要することが少なくありません。特に、海外での入学や入社日など期日が決まっている場合は専門家のサポートが不可欠です。精神的な負担を軽くし、より重要な準備に集中するためにも、専門家への依頼をご検討ください。
就労ビザ東京ドットコムは、外国人ビザ申請の専門家です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。
関連するオススメ記事はこちら
- フランス人を日本で雇用するための学歴要件とは?技人国(ぎじんこく)ビザは取れる?|グランゼコールと大学の違い、就労ビザ要件を行政書士が解説
- 【新規入国者必見‼】在留カードの住居地届出は14日以内!手続きの場所・持ち物を行政書士が解説します
- フィリピン人を日本で雇用するための学歴要件とは?技人国(ぎじんこく)ビザは取れる?大学(CHED)と専門資格(TESDA)の要件を徹底解説
- 補完的保護対象者とは?難民との違いや認定制度についてわかりやすく解説します!
- 【就職活動ビザ】学校卒業後に就職活動を行う留学生へ|必要書類と申請方法を解説します!
- 内定待機「特定活動ビザ」の申請方法について
- 台湾人を日本で雇用するための学歴要件とは?技人国(ぎじんこく)ビザは取れる?大学・専科学校別の要件と申請の注意点を解説
- 【特定活動】家事使用人ビザについて|高度専門職・特別高度専門職外国人などが雇用することが可能
- 【資格外活動許可】留学生がアルバイトをするには?
- 特定技能外国人の相談や苦情への対応方法について|登録支援機関

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史
2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート
