出国命令とは?退去強制との違いと、対象者について徹底解説
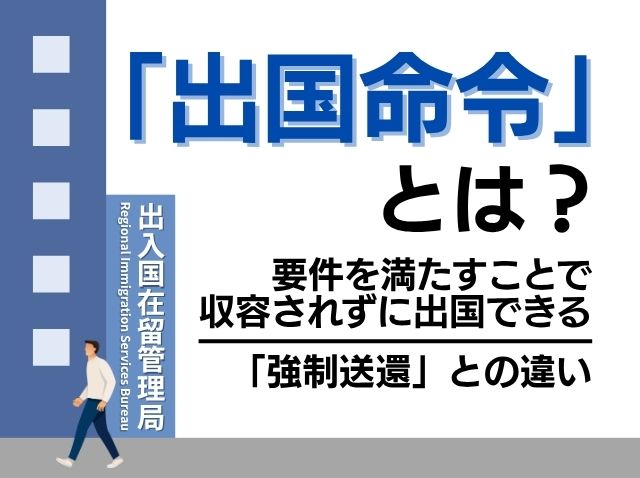
「外国人従業員の在留カードを確認したら、期限が切れていた…」
「このまま不法就労を続けると、会社にも罰則があるのだろうか?」
大切な従業員が、もしオーバーステイ(不法残留)の状態にあったら、経営者として大きな不安を感じるはずです。最悪の場合「退去強制」となり、二度と日本で働けなくなる可能性もあります。
しかし、諦めるのはまだ早いです。この記事では、そのような状況で利用できる出国命令制度について、退去強制との違いから、将来再び日本で働いてもらうための方法まで、ビザ申請の専門家が分かりやすく解説します。
この記事を最後まで読めば、解決方法を知り、会社と従業員の未来を守る具体的な方法を知ることができるでしょう。
オーバーステイで悩んでいませんか?強制退去になる前に知っておきたい「出国命令制度」
外国人従業員のオーバーステイ(不法残留)が発覚した際、多くの経営者様がどう対応すべきか頭を悩ませます。放置すれば、従業員本人はもちろん、雇用主である企業様にも厳しい罰則が科されるリスクがあります。
そのような絶望的な状況を回避するための選択肢が「出国命令制度」です。
このようなお悩みはありませんか?
現在、このようなことでお悩みではないでしょうか。一つでも当てはまるなら、この記事がきっとお役に立ちます。
- ビザの期限が切れてしまったが、どうすればいいか分からない
- 「退去強制」という言葉を聞いて、将来が不安で眠れない
- できれば、また日本で働きたいと考えている
- 誰に相談すればいいのか分からず、一人で抱え込んでいる
その悩み、「出国命令制度」で解決できるかもしれません。
出国命令制度とは、日本に不法に残留している外国人(オーバーステイなど)が、一定の要件を満たした場合に、身柄を収容されることなく簡易な手続きで出国できる制度です。
これは、自ら過ちを認めて出頭した人に対し、厳しい「退去強制」よりも軽い処分で出国を認める、いわば救済措置と言えます。この制度を正しく利用すれば、将来的な再来日への可能性を残すことができます。
【比較表】一目でわかる!「出国命令」と「退去強制」の3つの決定的違い
出国命令と退去強制は、どちらもオーバーステイなどの状態から出国に至る手続きですが、その内容は天と地ほど異なります。特に「身柄拘束の有無」と「再入国禁止期間」が、その後の人生を大きく左右するポイントです。
以下の表で、その違いを明確に理解しておきましょう。
| 項目 | 出国命令 | 退去強制 |
|---|---|---|
| 身柄の拘束 | 原則なし | 原則あり |
| 再入国禁止期間 | 1年 | 5年または10年 |
| 刑事罰 | 対象外 | 対象となる可能性あり |
出国命令制度を利用する3つのメリット
前述の比較表からも分かる通り、出国命令制度には退去強制と比べて大きなメリットがあります。従業員の将来を考えるならば、この制度の活用を第一に検討すべきです。
主なメリットは以下の3つです。
- 身柄を拘束(収容)されない
- 再入国禁止期間が1年と短い
- 刑事罰の対象にならない
それぞれ具体的に解説します。
1. 身柄を拘束(収容)されない
出国命令制度の最大のメリットは、原則として身柄を拘束されない点です。
退去強制の場合、発覚すると入管施設に収容されるのが一般的ですが、出国命令では自ら出頭し、出国までの間、普段通りの生活を送りながら準備を進めることができます。これは本人にとって、精神的・肉体的な負担を大幅に軽減できる非常に大きな利点です。
2. 再入国禁止期間が1年と短い(退去強制は5年または10年)
出国命令による出国の場合、日本に再入国できない期間(上陸拒否期間)は「1年」です。
これに対し、退去強制の場合は原則「5年」、過去にも退去強制歴があるなどの場合は「10年」と非常に長くなります。将来的に、再びその従業員を日本で雇用したいと考える経営者様にとって、この期間の差は事業計画にも影響する重要なポイントと言えるでしょう。
3. 刑事罰の対象にならない
出国命令制度に基づき出国する場合、不法滞在に関する刑事罰の対象にはなりません。
オーバーステイは「不法残留罪」という犯罪であり、本来は「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」が科される可能性があります。出国命令制度は、このような刑事手続きを経ずに、行政手続きのみで穏便に問題を解決する道筋を示してくれます。
あなたの未来のために、より有利な方法を選びませんか?
退去強制という厳しい処分を受けてしまうと、有能な人材が長期間日本に戻ってくる道が閉ざされてしまいます。これは従業員本人だけでなく、企業にとっても大きな損失です。
穏便に出国し、将来の再雇用への可能性を最大限に残すためにも、専門家への相談は不可欠です。
【セルフチェック】出国命令の対象となる5つの必須条件

出国命令制度は誰でも利用できるわけではありません。法律で定められた5つの条件をすべて満たす必要があります。自社の従業員が該当するか、まずは以下のリストで確認してみてください。
- 自ら入国管理官署に出頭したこと
- 不法残留(オーバーステイ)以外の退去強制事由に該当しないこと
- 過去に窃盗罪などで懲役または禁錮に処せられたことがないこと
- 過去に退去強制されたり、出国命令を受けたりしたことがないこと
- 速やかに出国することが確実と見込まれること
これらの条件について、一つずつ詳しく見ていきましょう。
1. 自ら入国管理官署に出頭したこと
この制度の最も重要な要件は、警察に逮捕されるなどではなく、「自らの意思で」最寄りの地方出入国在留管理局に出頭することです。
「このままではいけない」と自ら過ちを認め、自主的に申し出ることが大前提となります。発覚を恐れて隠れ続けるのではなく、勇気を持って一歩を踏み出すことが、より良い未来への第一歩となります。
2. 不法残留(オーバーステイ)以外の退去強制事由に該当しないこと
出国命令の対象は、在留期限を超えて日本に滞在してしまった「不法残留者」に限られます。
例えば、密航で入国した場合や、在留資格で許可された以外の活動(資格外活動)を無許可で行っていた場合など、オーバーステイ以外の退去強制理由がある場合は、この制度を利用することはできません。あくまで、純粋なオーバーステイ者が対象です。
3. 過去に犯罪で懲役または禁錮に処せられていないこと
日本への入国後、窃盗罪などの犯罪で懲役刑や禁錮刑に処せられたことがある場合は、対象外となります。
これは、日本社会の安全や秩序を守る観点からの要件です。交通違反による罰金など、比較的軽微な処分であれば問題ないケースもありますが、刑罰の種類によっては対象外となるため、正確な判断には専門的な知識が求められます。
4. 過去に退去強制されたり、出国命令を受けたりしたことがないこと
この制度は、あくまで「初めて」過ちを犯してしまった人向けの救済措置です。
したがって、過去に一度でも退去強制処分を受けたり、今回の出国命令制度を利用して出国したことがある場合は、二度目の利用は認められません。過去の出入国履歴がクリーンであることが求められます。
5. 速やかに出国することが確実と見込まれること
本人に出国の意思があり、かつ、出国するための航空券を自己負担で購入できるなど、物理的に出国が可能であると認められる必要があります。
出頭したものの、帰りの航空券を買うお金がない、パスポートの有効期限が切れていてすぐに再発行できない、といった状況では、速やかな出国が確実とは見なされず、制度を利用できない可能性があります。
出国命令を受けるための4つのステップと専門家に依頼するメリット

出国命令を受けるための手続きは、大まかに4つのステップで進みます。全体の流れを把握しておくことで、落ち着いて対応することができるでしょう。
- 最寄りの地方出入国在留管理局へ出頭
- 違反調査と入国審査官による審査
- 主任審査官による出国命令書の交付
- 出国期限内(15日以内)に日本から出国
各ステップと、専門家に依頼するメリットについて解説します。
1. 最寄りの地方出入国在留管理局へ出頭
まず、本人がパスポートや在留カードなどの身分証明書を持参し、地方出入国在留管理局に自ら出頭します。
この「出頭」という行為には、大きな勇気が必要です。専門家が同行することで、本人の精神的な負担を和らげ、手続きがスムーズに進むようサポートすることが可能です。どのタイミングで、どのような書類を持って出頭するのがベストか、事前にアドバイスいたします。
2. 入国審査官による違反調査
出頭後、入国審査官による違反調査が行われます。
ここでは、いつからオーバーステイになったのか、なぜそうなってしまったのか等の聞き取りが行われます。この聴取での受け答えは、出国命令を受けられるかどうかを判断する上で非常に重要です。専門家が事前に想定される質問を伝え、受け答えの準備をサポートすることで、不利な状況になるのを防ぎます。
3. 主任審査官による出国命令書の交付
調査の結果、出国命令の5つの要件をすべて満たしていると判断されると、主任審査官から「出国命令書」が交付されます。
この命令書には、出国すべき期限(原則として15日以内)が記載されています。この書類を受け取った時点で、退去強制ではなく、出国命令制度の対象となったことが確定します。ここまでの手続きを円滑に進めるのが、我々専門家の役割です。
4. 出国期限内(15日以内)に日本から出国
出国命令書に記載された期限内に、自費で航空券を手配し、日本から出国します。
空港での出国確認の際、出国命令書を提示する必要があります。無事に出国が完了すれば、一連の手続きは終了です。期限を過ぎてしまうと、出国命令が取り消され退去強制手続きに移行するため、厳守しなければなりません。
【重要】出国後の未来のために|再入国と就労ビザ申請の可能性

出国命令制度を利用して出国することは、ゴールではありません。むしろ、将来日本で再び活躍してもらうための新しいスタートです。
再入国禁止期間である1年が経過すれば、再び日本のビザを申請する権利が生まれます。そのチャンスを確実なものにするため、出国後の準備が非常に重要になります。
1. 再入国禁止期間(1年)の過ごし方
再入国禁止期間である1年間をどう過ごすかは、将来のビザ審査に影響します。
母国で、日本での職務内容と関連する仕事に就いたり、スキルアップに励んだりするなど、反省と向上の意欲を行動で示すことが重要です。単に1年間を無為に過ごすのではなく、日本への再貢献に向けた準備期間と位置づける意識が、後の審査官の心証を良くします。
2. 1年後の就労ビザ申請に向けた準備
再入国禁止期間が明けるタイミングに合わせて、就労ビザの申請準備を進めます。
この際、なぜ過去にオーバーステイに至ったのか、そしてそれに対して深く反省していることを示す「反省文(理由書)」の提出が極めて重要になります。過去の過ちを真摯に受け止め、二度と繰り返さないことを誓う説得力のある書類を作成する必要があります。
3. 採用企業への説明と協力の取り付け
再度のビザ申請には、受け入れ企業(雇用主)の強力なバックアップが不可欠です。
なぜその人材が再び必要なのかを具体的に説明した「採用理由書」や、安定した経営基盤を示す資料などを準備し、入管に対して「今回は企業が責任をもって管理監督する」という姿勢を明確に示す必要があります。企業側の協力体制が、許可の可能性を大きく左右します。
出国命令に関するよくあるご質問
ここでは、経営者様やご本人からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q1. 出頭する際、何を持っていけばいいですか?
A. パスポートと在留カード(所持している場合)は必須です。
その他、身元を証明できるものがあれば持参しましょう。また、出国するための航空券を既に予約している場合は、その予約票なども持っていくと、速やかな出国の意思を示す材料になります。具体的な必要書類は個別の状況によりますので、まずは専門家にご相談ください。
Q2. 費用はどのくらいかかりますか?
A. 出国命令制度自体の利用に、国へ支払う手数料はかかりません。
ただし、母国へ帰るための航空券代は、全額自己負担となります。専門家である行政書士に依頼する場合は、別途報酬が発生します。
Q3. 家族も一緒にオーバーステイしている場合はどうなりますか?
A. ご家族も、一人ひとりが出国命令の要件を満たしているか審査されます。
例えば、夫は要件を満たすが、妻が過去に退去強制歴がある、といった場合は、夫のみが出国命令、妻は退去強制となる可能性があります。家族全員での穏便な出国を望む場合は、全員の状況を正確に把握した上で、専門家と共に最善策を検討することが不可欠です。
Q4. 命令に違反して出国しなかった場合はどうなりますか?
A. 直ちに出国命令が取り消され、退去強制手続きに移行します。
さらに、不法残留罪として刑事告発される可能性も高まります。そうなると、再入国禁止期間は5年または10年となり、罰金や懲役刑が科されるリスクも生じます。与えられたチャンスを無駄にしないためにも、指定された期限は絶対に守らなければなりません。
まとめ:一人で悩まず、まずは第一歩を。あなたの未来へ繋がる無料相談はこちら
不法残留という状況は、経営者様にとっても従業員本人にとっても、非常に大きな不安を伴います。しかし、一人で悩み、時間を無駄にしていても状況は決して好転しません。むしろ、日に日にリスクは高まっていきます。
私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人35です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。
関連するオススメ記事はこちら
- 【特定活動57号】国際園芸博覧会関係者(56号)の配偶者と子を帯同するには
- 【就労ビザ】ビザを更新する方法とは?
- 特定技能外国人の生活オリエンテーションとは何をすべきなのか?
- ベトナム人を日本で雇用するための学歴要件とは?技人国(ぎじんこく)ビザは取れる?大学(Đại học)と短期大学(Cao đẳng)の要件と違いを徹底解説
- 高度専門職1号ロとは?文系職のポイント計算を行政書士が解説|技人国ビザとの違い
- 【2025年中開催予定】入国前結核スクリーニングについて|中長期在留者が対象
- 技術・人文知識・国際業務(ぎじんこく)とは|できる業務、要件を解説
- 【技能ビザ】料理人を呼び寄せる方法について|実務経験10年の証明と採用の要件を解説
- 外国人の口座が凍結される理由と対処方法について
- 【就労ビザ】申請人本人の法定代理人とは?

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史
2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート
