入管へのオンライン申請ガイド|準備する物・手順を日々の実務で活用している行政書士が解説します!
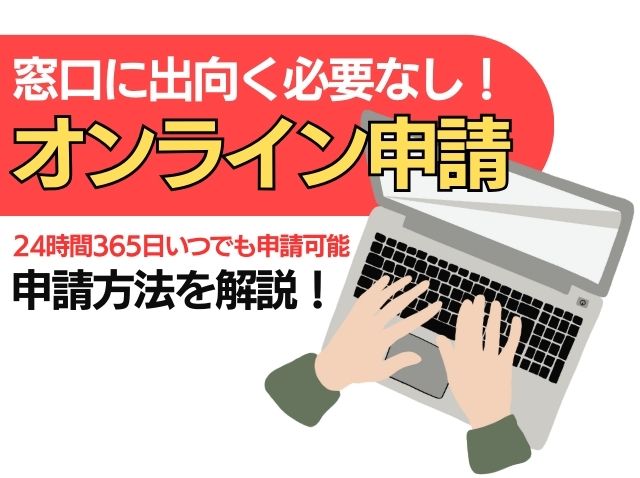
「在留資格の更新のために、業務を調整して入管へ行くのが負担だ」
「オンラインで申請できると聞いたが、準備が複雑そうで手が出せない」
外国人従業員の在留資格手続きを担当する企業の方や、日本で働く外国人ご本人から、このような声が聞かれます。
現在、就労ビザの更新や変更といった在留資格に関する手続きの多くは、出入国在留管理庁の「在留申請オンラインシステム」を利用し、ご自身のパソコンから24時間いつでも申請が可能です。
この記事では、日常的にオンライン申請を活用している専門の行政書士が、その利用準備から申請完了までの流れを、初心者の方にも分かりやすく解説します。
この記事を最後まで読めば、入管の長い待ち時間といった悩みから解放され、効率的な在留資格手続きの第一歩を踏み出せるでしょう。
在留資格のオンライン申請が標準に:24時間、場所を問わない手続きへ

これまで入管の窓口で行うのが一般的だった在留資格の申請は、今やオンラインで完結する時代へと移行しています。
この変化は、手続きの利便性向上だけでなく、企業の業務効率化にも直結する重要な動向です。
まずは、オンライン申請の基本と、そのメリットを把握しましょう。
1. 在留申請オンラインシステムとは
「在留申請オンラインシステム」とは、出入国在留管理庁が提供する、インターネットを通じて在留資格に関する各種申請を行える公式の電子申請システムです。
2019年の運用開始以来、対象となる手続きや利用者は年々拡大しています。
このシステムを利用することで、これまで入管の窓口へ出向く必要があった手続きの多くを、自宅やオフィスのパソコンから行えるようになります。
2. なぜ今オンライン申請なのか?企業の在留資格管理業務の効率化
オンライン申請の導入は、在留資格の管理業務を効率化する上で不可欠です。
担当者が移動や待ち時間に費やしていた時間を削減し、本来のコア業務に集中できます。
また、申請履歴や進捗状況がデータとしてシステム上に記録されるため、担当者が交代する際の引き継ぎも容易になり、属人化しがちな管理業務の標準化に繋がります。これは、企業にとって大きな生産性向上に貢献します。
3. 窓口申請との比較|メリット・デメリット
オンライン申請と従来の窓口申請には、それぞれメリットとデメリットがあります。
| 項目 | オンライン申請 | 窓口申請 |
|---|---|---|
| 申請時間 | 24時間365日(保守時を除く) | 平日9時~16時など限定的 |
| 場所 | 自宅やオフィスなど | 管轄の地方出入国在留管理局 |
| 待ち時間 | なし | 数時間に及ぶ場合あり |
| 交通費 | 不要 | 実費が発生 |
| 利用開始までの手間 | 機材購入、利用者登録が必要 | 不要 |
初期設定の手間を考慮しても、中長期的に見ればオンライン申請のメリットは非常に大きいと言えます。
オンライン申請の利用に必要なもの(準備リスト)
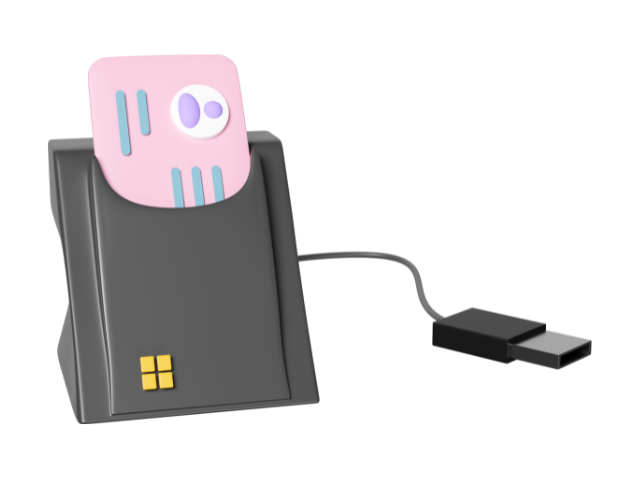
オンライン申請を始めるには、事前にいくつかの機材や情報を準備する必要があります。
以下のリストを参考に、一つずつ確認していきましょう。
1. パソコンとインターネット環境
WindowsまたはMacのパソコンと、安定したインターネット接続環境が必須です。
現時点では、スマートフォンやタブレット端末のみでの申請には対応していません。
2. マイナンバーカード
申請者の本人確認のため、マイナンバーカードが必須となります。
外国人ご本人が申請する場合はご自身のもの、企業の担当者が代理申請する場合はその担当者のものが必要です。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、まずはお住まいの市区町村で交付申請を行ってください。
3. ICカードリーダライタ
マイナンバーカードに記録された電子証明書を読み取るための専用機器です。
家電量販店やオンラインストアで数千円程度で購入できます。マイナンバーカードに対応した製品を選びましょう。
4. 申請書類(PDF形式)
申請に必要な書類(雇用契約書や決算書など)は、すべてスキャナ等で読み取り、PDF形式のファイルとして準備します。
紙媒体での提出は不要です。
5. 顔写真データ
縦4cm×横3cmの規格を満たす証明写真のデータ(JPEG形式など)が必要です。
写真店で撮影してデータを購入するか、データ保存機能付きの証明写真機を利用すると便利です。
利用登録から申請完了までの4ステップ
必要なものが揃えば、システムの利用を開始できます。
手続きは、大きく分けて以下の4ステップで進行します。
1. 在留申請オンラインシステムで利用者情報登録
まず、出入国在留管理庁の「在留申請オンラインシステム」のウェブサイトにアクセスし、「利用者情報登録」を行います。
画面の指示に従い、氏名、メールアドレス、在留カード番号などを入力します。企業の担当者が登録する場合は、法人情報なども入力します。
2. システムにログインし、申請情報を入力
利用者情報登録が承認されると、発行されたIDとパスワードでシステムにログインできます。
マイナンバーカードをICカードリーダライタで読み取って本人認証を行い、申請種別(更新、変更など)を選択して、必要事項を入力していきます。
3. 必要書類(PDF)と顔写真データをアップロード
事前に準備した、申請書類のPDFファイルと顔写真データをシステム上にアップロードします。
ファイルサイズに上限があるため、容量が大きい場合は圧縮するなどの対応が必要です。
4. 申請内容を確認し、送信(申請完了)
最後に入力内容やアップロードした書類に誤りがないかを確認し、「申請」ボタンをクリックします。
これで申請は完了です。審査の進捗状況は、いつでもシステム上で確認できます。
オンライン申請の注意点と実務上のポイント
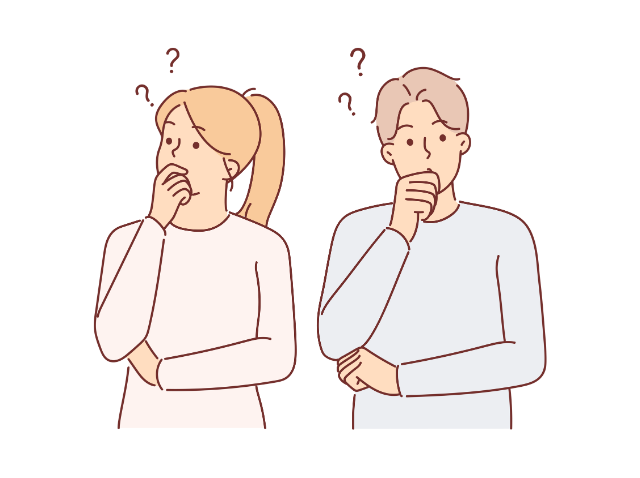
オンライン申請は非常に便利ですが、いくつか注意すべき点があります。
専門家が実務でよく遭遇する、初心者がつまずきやすいポイントをご紹介します。
1. PDFファイルのサイズ制限と結合
システムにアップロードできるPDFは、1ファイルあたりの容量に上限が設けられています。
高解像度でスキャンすると上限を超えることがあるため注意が必要です。また、複数の書類を1つのPDFファイルにまとめる「結合」作業が求められる場面もあります。事前にPDFの圧縮・結合ができるツールを用意しておくとスムーズです。
2. 顔写真データの規格
顔写真のデータには、ピクセル数やファイルサイズ、背景色など、詳細な規格が定められています。
規格外のデータをアップロードすると、申請が受理されなかったり、撮り直しを指示されたりする原因となります。規定をよく確認しましょう。
3. システムエラーの発生
まれに、お使いのブラウザのバージョンや設定が原因で、システムが正常に動作しないことがあります。
公式サイトで推奨されている利用環境を確認し、それでもエラーが出る場合は、時間をおいて再度試すか、別のパソコンで操作するなどの対応が有効です。
オンライン申請の対象範囲
オンライン申請は、年々対象となる手続きが拡大しています。
現在、どのような手続きがオンラインで可能なのでしょうか。
1. 対象となる主な在留資格
「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザをはじめ、「経営・管理」「留学」「家族滞在」など、ほとんどの在留資格がオンライン申請の対象です。
また、高度専門職の在留資格申請もオンラインで行えます。
2. 対象となる手続きの種類
以下の主要な手続きがオンライン申請に対応しています。
- 在留資格認定証明書交付申請(海外からの招聘)
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格取得許可申請(日本での出生時など)
- 就労資格証明書交付申請(転職時など)
就労ビザのオンライン申請に関するよくある質問
最後に、オンライン申請に関してよくいただく質問にお答えします。
Q. オンライン申請と窓口申請で、審査期間に違いはありますか?
A. 公式には審査期間に差はないとされていますが、実務上の感覚では、オンライン申請の方が比較的早く結果を受領する傾向があります。
これは、書類が電子化されていることで、審査官が内容を確認しやすくなるためと考えられます。
Q. 手数料(収入印紙)の値段はいくらですか?
A. 窓口申請よりも若干安くなっています。
例えば、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請の場合、窓口申請ですと手数料6,000円ですが、オンライン申請の場合には5,500円となりますので、若干費用をおさえることが可能です。
Q. スマートフォンだけでも申請できますか?
A. いいえ、できません。必ずパソコンが必要です。
マイナンバーカードを読み取るICカードリーダライタの接続や、システムの仕様がパソコンでの利用を前提としているためです。
まとめ:オンライン申請の活用で、在留資格手続きを効率化する
今回は、在留資格のオンライン申請について、その準備から完了までの流れを解説しました。
最初の機材準備と利用者登録というステップをクリアすれば、オンライン申請は在留資格手続きを劇的に効率化し、時間とコストを大幅に削減します。
もう、悪天候の中を入管へ赴き、長時間待つ必要はありません。
就労ビザ東京ドットコムは、外国人ビザ申請の専門家です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。
関連するオススメ記事はこちら
- 【資格外活動許可】留学生がアルバイトをするには?
- 就労資格証明書とは?外国人の中途採用(転職)にはあると安心!
- 特定技能外国人の相談や苦情への対応方法について|登録支援機関
- 特定技能外国人の日本語学習の機会提供について|登録支援機関
- 申請後の審査期間について|就労ビザ
- 就労ビザ申請時のポイント⁉:『審査のスピード』は会社の規模で変わるのか?
- 個人事業主でも外国人雇用はできるのか?就労ビザ取得のポイントを解説
- 特定技能外国人の日本人との交流促進について|登録支援機関
- 特定技能へ変更するための移行準備ビザとは?6月の猶予が与えられます|在留資格「特定活動」
- インド人を日本で雇用する際の学歴要件とは?技人国(ぎじんこく)ビザは取れる?|「10+2+3」制からIITまで図解でわかる

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史
2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート
