ビザ申請を行う入管の場所はどこ?管轄と問い合わせ先を解説
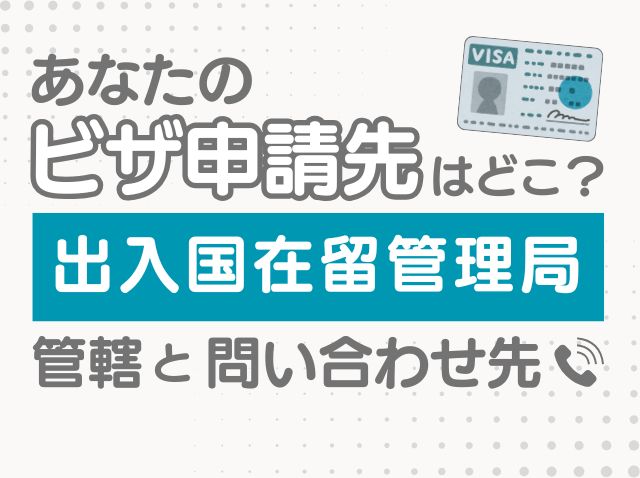
日本での新しい生活やキャリアのスタート、あるいは滞在の継続に不可欠なビザ(在留資格)の申請。
しかし、いざ手続きを始めようとすると
「一体どこの出入国在留管理局(入管)に行けばいいのだろう?」
「申請書類について、どこに問い合わせれば正確な情報が得られるの?」
といった基本的な疑問に直面する外国人の方や、そのサポートをされる方は少なくありません。
この最初のステップである「正しい窓口の特定」は、その後の手続きをスムーズに進める上で非常に重要です。
日本の出入国在留管理は全国規模で行われており、申請する内容やお住まいの地域によって、担当する入管の窓口が異なります。
また、一般的な問い合わせから個別具体的な相談まで、内容に応じて適切な連絡先を選ぶ必要があります。
間違った場所に申請書類を提出してしまったり、見当違いの窓口に問い合わせてしまったりすると、時間と労力が無駄になるだけでなく、最悪の場合、申請期限に間に合わないといった事態も招きかねません。
この記事では、2025年の最新情報に基づき、日本に在留する外国人の方が各種ビザ申請(在留資格関連手続き)を行う際に、ご自身の住所地を管轄する出入国在留管理局や支局・出張所をどのように見つけるか、そして一般的な手続きに関する問い合わせから、より専門的な相談まで、目的に応じた正しい問い合わせ先はどこなのかを、全国的な視点から分かりやすく解説します。
この記事を読めば、あなたがどの窓口に行くべきかが明確になり、ビザ申請の準備を安心して始めることができるでしょう。
目次
- まずは基本!「出入国在留管理庁」とその役割
- 【重要】ビザ申請はどこで行う?「管轄」の考え方と調べ方
- 【あなたの街はどこ?】全国の主な地方出入国在留管理局・支局の所在地と連絡先例
- ビザ手続きに関する「問い合わせ」はどうすればいい?主な相談窓口と方法
- 【まとめ】正しい窓口を選び、スムーズなビザ申請を
まずは基本!「出入国在留管理庁」とその役割
外国人の方のビザ(在留資格)に関する申請や問い合わせについて考える前に、まず日本の出入国管理行政の中心的な役割を担っている「出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)」、通称「入管庁(にゅうかんちょう)」または単に「入管(にゅうかん)」と呼ばれる組織について、基本的な情報を押さえておくことが大切です。
入管庁がどのような組織で、何をしているのかを理解することで、各種手続きの背景や目的が見えてくるでしょう。
出入国在留管理庁は、日本の法務省に属する外局の一つです。
主な任務は、日本に出入りする全ての人(日本人を含む)の出入国審査を行うこと、そして日本に滞在する外国人の在留資格の審査や管理、さらには難民の認定手続きなど、国の安全と公正な出入国管理を実現するための幅広い業務を担当しています。
2019年4月に、それまでの法務省入国管理局が改組され、より強力な権限と体制を持つ「庁」として新たにスタートしました。
入管庁の具体的な業務内容は多岐にわたりますが、外国人の方に特に関連が深いものとしては、まず在留資格に関する各種審査と許可が挙げられます。
日本で働きたい、学びたい、家族と暮らしたいといった様々な目的で滞在を希望する外国人からの申請(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請など)を受け付け、法律や基準に基づいて審査し、許可・不許可の決定を行います。
この審査の過程で、申請された内容が事実であるか、また日本の法律に適合しているかなどが厳しくチェックされます。
また、日本に入国する際の上陸審査や、日本から出国する際の出国確認も入管庁の重要な業務です。
空港や港に配置された入国審査官が、パスポートやビザ(査証)の確認、入国目的の聴取などを行い、日本への入国が適当かどうかを最終的に判断します。
さらに、日本国内での在留カードの発行や管理も入管庁の仕事です。
中長期的に日本に滞在する外国人には在留カードが交付され、在留カードは日本での身分証明書として非常に重要な役割を果たします。
残念ながら、日本に不法に滞在している外国人や、在留資格で許可された範囲を超えた活動を行っている外国人に対する調査、収容、そして退去強制手続きも、入管庁が担う厳しい側面の一つです。
一方で、国際的な責務として、難民条約等に基づく難民認定の手続きも行っています。
出入国在留管理庁が担うこれらの幅広い業務を全国的に、かつ効率的に行うため、入管庁は東京に本庁を置くほか、日本全国を8つのブロックに分け、それぞれを管轄する地方出入国在留管理局(例:東京出入国在留管理局、大阪出入国在留管理局など)を設置しています。
そして、各地方局の下には、さらに業務を分担する支局(空港支局や主要都市の支局)や、より地域に密着した窓口となる出張所が配置されています。
ビザ申請や問い合わせの際には、原則として自分の住んでいる地域や、受け入れ先の会社の所在地を管轄するこれらの地方機関が窓口となります。
このように、出入国在留管理庁は、日本の国境管理と国内の外国人管理を一手に担う、外国人の方々の日本での生活に深く関わる行政機関です。
次のセクションでは、具体的にどの入管が自分の申請や問い合わせを担当するのか、「管轄」の考え方について詳しく見ていきましょう。
【重要】ビザ申請はどこで行う?「管轄」の考え方と調べ方
日本でビザ(在留資格)に関する各種申請、例えば在留資格認定証明書の交付申請、在留資格の変更許可申請、あるいは在留期間の更新許可申請などを行う際には、どの出入国在留管理官署に申請書類を提出するかが非常に重要になります。
日本全国に数多く存在する出入国在留管理庁の地方局、支局、出張所の中から、ご自身のケースに対応してくれる正しい窓口を選ぶ必要があるのです。
この「正しい窓口」のことを、法律用語で「管轄(かんかつ)」と呼びます。
原則として、ビザに関する申請は、申請を行う外国人の方の「住居地」(住民票のある場所)か、あるいは外国人を雇用したり受け入れたりする「受入れ機関(会社や学校など)の所在地」を管轄する地方出入国在留管理官署が申請先となります。
例えば、東京都内に住んでいる方が就労ビザの更新をする場合は、東京出入国在留管理局が管轄となります。
大阪府に本社がある企業が海外から外国人を呼び寄せる(在留資格認定証明書交付申請)場合は、大阪出入国在留管理局が管轄となります。
では、ご自身の住居地や受入れ機関の所在地を管轄する出入国在留管理官署は、どのように調べればよいのでしょうか。
最も確実な方法は、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトで確認することです。
ウェブサイトには、全国の地方出入国在留管理局、支局、出張所の一覧と、それぞれが管轄する市区町村が明記されています。
お住まいの都道府県や市区町村名から、担当する入管窓口を見つけることができます。もしウェブサイトでの確認が難しい場合は、後述する「外国人在留総合インフォメーションセンター」に電話で問い合わせるという方法もあります。
ここで注意が必要なのは、申請する手続きの種類によっては、必ずしも最寄りの出張所で全ての申請が受け付けられるわけではないという点です。
例えば、一部の出張所では在留資格認定証明書交付申請を取り扱っていない場合があったり、永住許可申請は地方局本局でしか受け付けていなかったりすることがあります。
また、成田空港や関西国際空港などにある空港支局は、主に出入国手続き(上陸審査や出国確認)に特化しており、日本国内で行う在留資格の変更や更新といった手続きは通常取り扱っていません。
そのため、申請前には、訪問しようとしている入管窓口が目的の申請手続きを取り扱っているかどうかも併せて確認することが非常に大切です。
次のセクションでは、日本全国に設置されている主要な地方出入国在留管理局と、その代表的な支局・出張所の所在地や連絡先について、具体例を挙げてご紹介します。
【あなたの街はどこ?】全国の主な地方出入国在留管理局・支局の所在地と連絡先例
日本全国のビザ(在留資格)申請は、出入国在留管理庁が設置する地方機関が担当しています。
具体的には、全国に8つの主要な「地方出入国在留管理局」があり、それぞれの地方局が広範な地域を管轄しています。
さらに、各地方局の下には、より細分化されたエリアを担当する「支局」や「出張所」が設けられています。
ここでは、主要な地方出入国在留管理局と、その代表的な窓口の例をいくつかご紹介しますが、これはあくまで一般的な情報提供であり、必ずご自身の申請内容や居住地に合わせて、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトで最新かつ正確な情報を確認してください。
例えば、首都圏および関東甲信越地方にお住まいの方は、多くの場合、東京出入国在留管理局(本局所在地:東京都港区)またはその管轄下の支局・出張所(例:立川出張所、さいたま出張所、千葉出張所、横浜支局など)が申請先となります。
東京出入国在留管理局の本局は非常に規模が大きく、多くの申請者が訪れますが、申請する在留資格の種類や居住地によっては、最寄りの支局や出張所で対応可能な場合もあります。
近畿地方(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県)にお住まいの方の多くは、大阪出入国在留管理局(本局所在地:大阪市住之江区)またはその管轄下の支局・出張所(例:神戸支局、京都出張所など)が窓口となります。
大阪出入国在留管理局も大規模な官署の一つです。
中部地方では、名古屋出入国在留管理局(本局所在地:名古屋市港区)が愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、福井県、石川県、富山県を管轄しています。
九州・沖縄地方では、福岡出入国在留管理局(本局所在地:福岡市中央区)が窓口となり、沖縄県には那覇支局が設置されています。
このほか、北海道を管轄する札幌出入国在留管理局、東北地方を管轄する仙台出入国在留管理局、中国地方を管轄する広島出入国在留管理局、四国地方を管轄する高松出入国在留管理局が、それぞれ管轄地域の申請業務を担っています。
各地方出入国在留管理局や支局、出張所の具体的な所在地、電話番号、そして何よりも重要な窓口の受付時間や取り扱い業務の種類は、必ず事前に出入国在留管理庁の公式ウェブサイトで確認するようにしてください。
ウェブサイトには、各官署へのアクセス方法や地図も掲載されています。電話での問い合わせも可能ですが、時間帯によっては繋がりにくいことがあるため、まずはウェブサイトで情報を探すのが効率的です。
繰り返しになりますが、申請先の官署を間違えると、申請が受理されなかったり、大幅な時間のロスに繋がったりする可能性があります。正確な管轄情報を事前に把握することが、スムーズなビザ申請の実現に不可欠です。
次のセクションでは、ビザ手続きに関する一般的な疑問や相談をどこにすればよいのか、主要な問い合わせ窓口とその利用方法について解説します。
ビザ手続きに関する「問い合わせ」はどうすればいい?主な相談窓口と方法
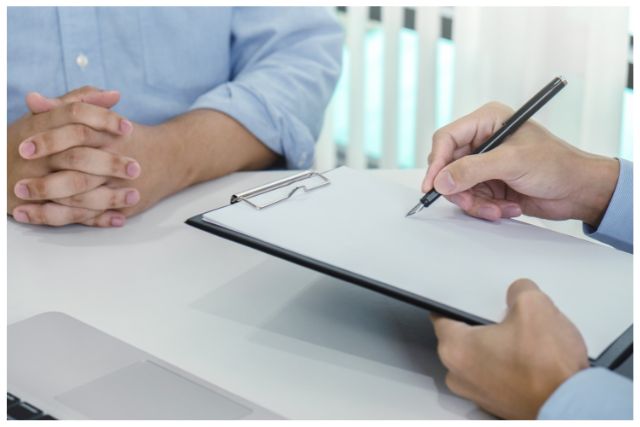
ビザ(在留資格)の申請準備を進めていると
「この書類で本当に合っているのだろうか?」
「申請書のこの項目はどう書けばいいの?」
など、様々な疑問や不安が生じることがあります。
そんな時、どこに問い合わせれば正確な情報を得られるのかを知っておくことは非常に重要です。
出入国在留管理庁(入管庁)は、外国人の方々からの問い合わせに対応するために、いくつかの相談窓口を設けています。
ここでは、主な相談窓口とその利用方法、そして問い合わせる際の注意点について解説します。
まず、最も一般的な問い合わせ先として「外国人在留総合インフォメーションセンター」があります。
外国人在留総合インフォメーションセンターは、全国の地方出入国在留管理局・支局などに設置されており、入国・在留に関する一般的な手続きや申請書類の書き方、必要書類などについての質問に、多言語で対応してくれます。
電話での問い合わせが主で、全国共通のナビダイヤル(0570-013904)にかけると、最寄りのセンターに繋がるか、専門のオペレーターが対応します。
IP電話や海外からの場合は、専用の番号(例:東京は03-5796-7112)が用意されています。受付時間は通常、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
ただし、電話が非常に混み合い、繋がりにくい場合があること、特に休み明けなどは注意が必要です。
また、メール(info-tokyo@i.moj.go.jp など、窓口により異なる)でも日本語と英語で問い合わせが可能ですが、個別の申請状況や許可の見通しについては回答を得られません。
より専門的で多角的なサポートを求める場合は、「外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)」の利用も検討できます。
FRESCは東京都新宿区にあり、入管庁だけでなく、法務局、ハローワーク、日本司法支援センター(法テラス)など、外国人の在留支援に関わる複数の機関が一堂に会したワンストップ型の相談拠点です。入管庁のブースでは、予約制で在留資格に関する対面相談やオンライン相談を多言語で行っています。
電話(代表ナビダイヤル:0570-011000)での問い合わせも可能です。
個別の申請に関する具体的な問い合わせや、既に申請を提出した案件の進捗(ただし詳細な審査内容は不可)については、申請を提出した、または提出予定の地方出入国在留管理局、支局、出張所の担当窓口に直接確認する方法もあります。
各官署の代表電話番号は入管庁のウェブサイトで確認できますが、審査部門など特定の部署は電話が非常に繋がりにくいのが実情です。
また、窓口での相談も可能ですが、混雑している場合が多く、長時間待つこともあります。東京出入国在留管理局(品川庁舎)の代表電話はナビダイヤル0570-034259(IP電話等からは03-5796-7234)です。
問い合わせを行う際には、事前にご自身の状況や質問内容を整理しておくことが大切です。
また、個別の申請の許可見込みや審査の進捗状況の詳細については、原則としてどの窓口でも回答を得ることは難しいと理解しておきましょう。一般的な手続き案内や必要書類の確認が主な対応範囲となります。
【まとめ】正しい窓口を選び、スムーズなビザ申請を
外国人の方が日本で生活や仕事をするために必要なビザ(在留資格)の申請や、それに関する問い合わせは、適切な窓口を選び、正しい手順で行うことが非常に重要です。
最後に、スムーズな手続きのための重要なポイントを改めて確認しましょう。
ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更・更新許可申請など)は、原則としてご自身の住居地、または受け入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局、支局、出張所が窓口となります。
管轄を間違えると申請が受理されないため、事前に必ず入管庁の公式ウェブサイトで確認するか、電話で問い合わせることが不可欠です。
全国には8つの地方局があり、その下に支局や出張所が置かれていますが、全ての窓口で全ての申請が扱えるわけではない点にも注意が必要です。
一般的な手続きに関する疑問や相談は、まず「外国人在留総合インフォメーションセンター」へ電話(ナビダイヤル:0570-013904)またはメールで問い合わせるのが良いでしょう。
多言語に対応しており、基本的な情報提供を受けることができます。
より専門的な相談や包括的な支援を求める場合は、東京にある「外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)」も有効な選択肢です。
個別の申請状況に関する問い合わせは、申請を提出した官署が基本となりますが、審査状況の詳細な回答は難しい場合が多いことを理解しておきましょう。
2025年においては、多くの在留申請手続きでオンライン申請が可能になっており、利便性が向上しています。
また、同年4月1日から申請手数料が改定されているため、申請時には最新の金額を確認する必要があります。
入管庁のウェブサイトでは、制度変更やシステムメンテナンス(例:2025年4月のメール配信サービス一時停止)に関する情報が随時「更新情報」として掲載されますので、定期的なチェックを怠らないようにしましょう。
正確な情報収集、適切な窓口の選択、そして余裕を持った申請準備が、複雑なビザ手続きを円滑に進めるための鍵となります。
私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。
関連するオススメ記事はこちら
- 特定技能外国人は転職ができるのか?条件や申請方法、注意点などを徹底解説
- ロシア人を日本で雇用するための学歴要件とは?技人国(ぎじんこく)ビザは取れる?|スペシャリスト学位・就労ビザ要件を行政書士が解説
- 2025年最新版【記入例あり】在留期間更新許可申請書の書き方を徹底解説
- 特例期間とは?在留期間満了後に発生する期間です。条件と注意点を解説!
- インターンシップビザ(特定活動)について|海外・国内学生別の必要手続きを専門家が解説
- ドイツ人を日本で雇用する場合の学歴要件とは?技人国(ぎじんこく)ビザは取れる?|就労ビザの取得要件など行政書士が解説
- 特定技能へ変更するための移行準備ビザとは?6月の猶予が与えられます|在留資格「特定活動」
- 特定技能に必要な日本語試験について|種類・レベル・対策・合格のコツとは?
- 韓国人を日本で雇用するための学歴要件とは?技人国(ぎじんこく)ビザは取れる?「専門大学」の要件まで徹底解説
- 【入管へ納付】ビザ申請後の手数料はいくらかかるの?|収入印紙|就労ビザ

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史
2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート
